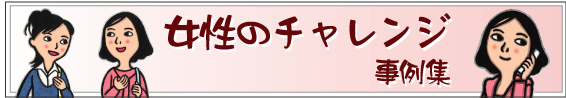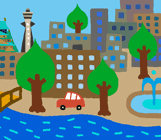留学したアメリカで出会った ソーシャルワークがライフワークに
尾崎礼子さん

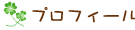
米国・オハイオ州で主にDV被害者支援関連のトレーニングと加害者対策に携わる。
著書に「DV被害者支援ハンドブック〜サバイバーとともに」(朱鷺書房)。
留学中、淋しさに声をあげて泣いたこともあるという尾崎さん。その彼女を支えたのは「このままでは帰れない」との思いと、「差別を知った瞬間」の記憶だった。
はじめて知った女性差別
尾崎さんには「原点」となる出来事がある。日本で外資系企業に勤めていたときのことだ。「その会社には一日に3回お茶を入れる習慣があったんですが、後輩の男性社員がいるのに先輩の女性がお茶を入れていたんです。『どうして彼がお茶を入れないの』とたずねると『彼は男性だからいいのよ』って。びっくりしました。確かに私も毎日お茶汲みしていましたが、それは私が一番新入社員だから、と思っていたんです」。尾崎さんが、はじめて知った「女性差別」だった。
それから、気をつけて周囲を見ると、男性社員がどんどん責任ある仕事を任されていくのに、女性社員は何年たっても男性社員のアシスタント業務ばかりをさせられている。「そこで、何かスキルがあれば男女の差なく仕事ができるのではないか、と考えたんです。アメリカへ行って本場で英語を学べば、通訳というスキルで勝負できる仕事につけると思いました」。
ソーシャルワークとの出会い
アメリカでは「とにかく学費の安いところ」と、ルイジアナ州で大学付属の英語学校の外国人コースに入学する。ここでみっちりと英語力をつける予定だった。「自分では大して英語ができるとも思えないのに、上級レベルのクラスに入れられたんです。もっと英語が学べると思ったのに、と思いました」。
通訳になるためには単に英語が話せるだけでなく専門分野が必要だと考え、大学に進学することにした。どの学位を取得しようかと図書館で調べているとき、「ソーシャルワーク」と出会う。それまで聞いたこともない言葉だったが、人種差別・性差別などの不公平を正し、マイノリティの支援に取り組んでいくと知って、関心を持った。「日本での経験で私はすでに差別に対してとても鋭敏な感性をもっていましたし。それにルイジアナはアメリカでも歴史的に人種差別の激しいところなんです。私自身もマイノリティとしてその現実を体感したこともあり、ソーシャルワークを専攻することに迷いはありませんでした」。そこで、この分野で通訳になろうと、ペンシルバニア州の小さな大学に入学したが、いつの間にか通訳ではなく、ソーシャルワーカーになることが目標になっていた。日本に帰国し、働いて学費を貯めては、また渡米して勉強を続けることを繰り返す日々だった。
「このままでは帰れない」
「留学中、辛いと思ったことはありませんか」とたずねると、「声を上げて泣いたこともありますよ。でも、日本に帰ろうとは思いませんでした。今、帰ったら、これまで何のためにやってきたのか分からなくなる、とにかく行けるところまで行きたい、という思いの方が強かったですね」。
現在、アメリカで、DV加害者のグループワークをはじめDVについての専門家研修などさまざまな活動を行っている尾崎さん。今後はアメリカでの実践を生かして日本のDV被害者支援、加害者対策にも貢献したいと考えている。
|